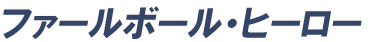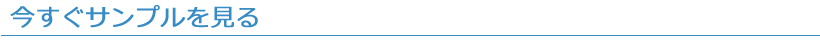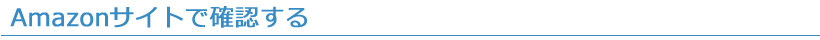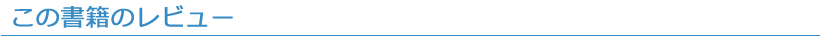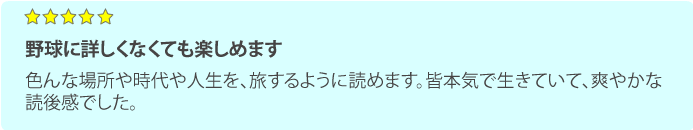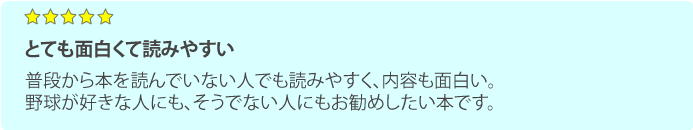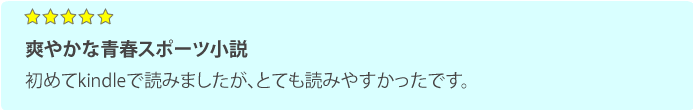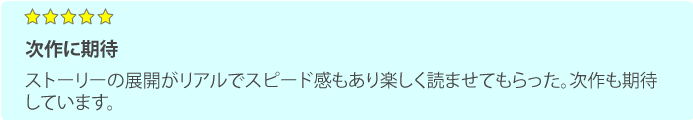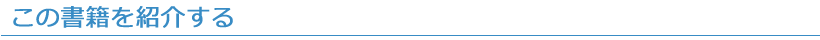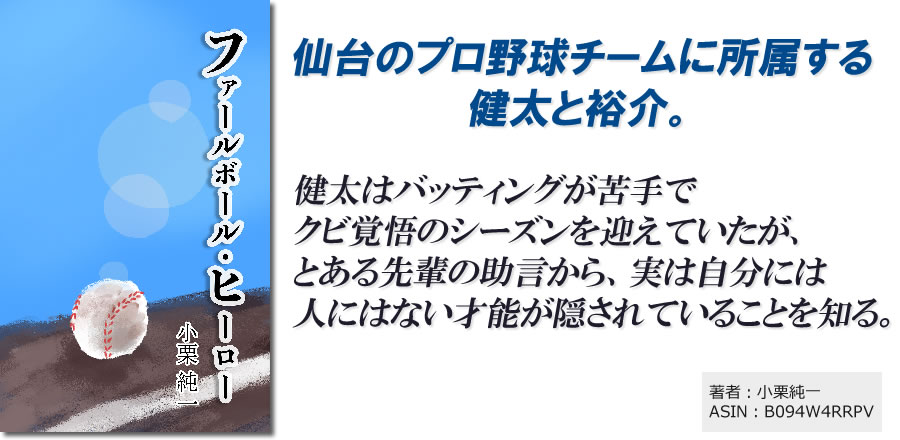
AI音声解説
再生ボタンを押すとAI音声のナレーションを聞くことができます。

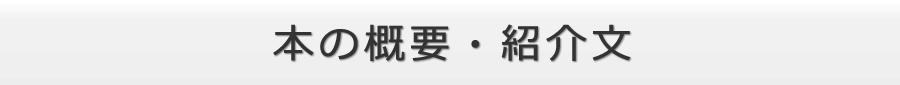

仙台のプロ野球チームに所属する健太と裕介。
健太はバッティングが苦手でクビ覚悟のシーズンを迎えていたが、
とある先輩の助言から、実は自分には人にはない才能が隠されていることを知る。
また裕介に野球を教え、早くして世を去った亡き父卓夫の前世に関する驚くべき事実が明らかになる。
健太と裕介の友情と、二人に思いを寄せる看護師のはるか。
それぞれの家族が織りなす不思議な運命と絆。
物語は思わぬ展開を見せる。



人は誰しも人生を振り返り、岐路に差し掛かり選択を迫られた瞬間を思い起こすことがあるだろう。この年の夏から秋にかけての三カ月足らずの間に、僕は野球という自ら選んだ生業と、家族の絆という誰も逃れることの出来ない宿命との狭間で、正に苦渋の決断を体現した。
あの時、外野のフェンスを越え、打ち上げられたロケット花火のように空の彼方に消えて行く硬球を、僕は不思議な気持ちで見送っていた。
―――あれは、本当に僕が今打ち返したボールだろうか?いや、僕にそんな力がある筈がない。それは失った物の尊さと大きさを自らに思い知らせるための、神様の皮肉を込めた悪戯だったのか、それとも夢の代償として得た未来への祝砲のオマージュだったのか。その答えを知るのはまだ先のことだろうし、そんな問いかけ自体が無意味なことかもしれない。なぜなら、人生に〝過ち〟はあっても〝正解〟だったという答えは、永遠に得られないのだから。
8月22日(火) 石黒健太
〝カーン!〟、夏空に白球音がこだました。グラウンドでは、セミの鳴き声に負けない程の、「オーライ、オーライ」というあの野球選手独特の掛け声が飛び交っていた。ひと練習を終えた石黒健太は、まるでそうする事がスポーツ選手の特権であるかのように、水道の蛇口に直に口をつけ、旨そうに水をがぶ飲みした。そして流れる汗をタオルで拭い、ギラギラ輝く太陽を眩しそうに見上げた。
―――それにしても、暑いぜ。
『太陽のように、いつも健やかに輝いていて欲しい。』
親から名前の由来を聞かされたことがあるが、こう毎日晴天続きで雨が降らないと逆にこまったものだ。新聞やニュース報道でも、社会的な水不足が取りざたされている。今日は午後、二軍の公式戦があるので、珍しく宮城野の本拠地スタジアムだが、いつもの泉練習場のように人工芝ではない土のグラウンドでは、練習時の水まきが大変である。雨が降ってくれれば試合は中止になり、練習はもちろん冷房の効いている室内練習場で行われる。
「真っ赤に燃ーえるー、太陽だーからー、真夏の海は、ああ海に生きてェ・・・。」
健太は、子どものころ父がいつも唄っていた古い歌を口ずさみ、もう一度恨めしそうに太陽を見上げた。
「おい健太、いくぞ!」
河上コーチの号令がかかった。グラブを手にした健太はポジションのショートに走り、同じポジションの先輩松原の後ろについた。
「俺に遠慮はいらんぞ。先輩だと思うな、ライバルを蹴落とすつもりでやれ!」
松原の熱い激励は嬉しかった。ノックが始まり、二人は交互にコーチの放つ勢いのあるゴロを、右に左に飛びついて処理し始めた。守備練習は大好きだ。一人で受ける100本ノックも嫌だと思ったことがない。ユニフォームの膝や胸が真っ黒に汚れていくことすら、快く感じられる健太だった。
健太は、名古屋の社会人野球チームで活躍していたところを、楽々ゴールデンリーガルスからドラフト5位で指名され、今年で入団三年目になる。
彼の持ち味は、百メートル十一秒を切る走力と肩の強さ、選球眼、そして何といってもその確実な守備力である。昨年の二軍の公式戦では、失策数0を誇る。しかしバッティングに関しては、入団当初は平均的であったが、最近はからきし打てなくなった。健太自身、最近のバッティングの成績では、一軍に上がるどころか、来年あたり戦力外通告をされる危機感さえ持っていた。
―――このままでは、いけない。何とか活路を見出さなければ・・・。
そんな気持ちとは裏腹に、この日も健太は練習で、バッティングピッチャーの投げるくせ球を、まともにはじき返すことが出来なかった。気の毒に思ったのか、彼が途中から打ちやすい球を投げてくれているのがよく分かったが、結果は殆んどヒット性の当たりはなく、右に左にそして後ろにむなしくゴロが転がっていった。足があるので、塁にさえ出れば何とかなる・・と、健太の隠れた才能を引き出そうとスタメンで使い続けてくれている監督の温情に応えるためにも、実戦の試合で結果を出したい健太だった。
子どもの頃は背は高い方だったが、どちらかと言えばたくましいタイプではなく、サッカーやバレーボールなどの球技は苦手だった。ただ走るのは得意で、運動会の徒競走はいつも一等賞だった。性格は素直で決して反抗的ではなかったが、おとなしいというより無気力、無愛想、かつ無口だった。例えば朝出かける時、『行ってらっしゃい,きょうは何時頃帰るの?』と母がたずねると、『5』と答え、弁当を作った母が、『おにぎり、いくつ入れておくの?』と聞くと、『3』と返事をして、父に『ちゃんと5時と答えなさい。』、『3個と言いなさい。』と、よく叱られたものだった。そして、朝出かける時、
「きょう、友達連れて帰る。」
「何人?」
「1(いち))。」
母は思わず絶句した。
母紀子は健康でおおらか、性格は明るく、音楽好きで、昔からレコードでいつもオペレッタをかけて聴いていたものだ。今も時々CDを聞きながら台所に立ったり、掃除をしながら鼻歌を歌っている。
「だって、オペレッタは必ずハッピーエンドなんだもの。」
母は、口癖のようにこう言っていた。ちなみにほとんどのオペラは、必ず主人公が死んでしまうそうだ。そんな母の一番のお気に入りの曲は、『メリー・ウィドー(陽気な未亡人)』というオペレッタの主題歌、『メリーウィドー・ワルツ』という曲で、子供の頃からよく聞かされていた健太は、この曲のメロディーだけは、今でもそらんじて歌えるほどだ。
健太は高校一年の時、野球部の顧問をしていた担任山元に勧められて野球を始めた。
「石黒は、部活やらないのか?」
「えっ、ぼくですか。特に考えていません、のんびりとしてて性格も消極的ですし。」
「もったいないな。この間の体育の時間に100メートル走を測定しただろう?お前が速いのでびっくりしたよ、学年で断トツの1位だったぞ。」
「子供の頃から走るのは速かったです、ピンポンダッシュとか。」
「どんな高校生活を送るかはお前の自由だが、どうだ?たった一度の青春、野球に賭けてみないか?」
「野球ですか、近所の公園でのガキ同士のお遊び程度にしかやったことないです。」
「誰だって初めは、キャッチボールに草野球からだ。」
なかば強引な勧誘に負けた形で入部し、スタートとしては遅かったが、もともと素質があったのかめきめきと才能を発揮し、卒業する頃はキャプテンになっていた。当然性格もがらりと変わり、明るく積極的になった息子を、両親は頼もしく喜びを持って見ていた。そして卒業後は大学には行かず、父の仕事関係の名古屋の有名な自動車会社の野球部に就職した。
健太の実家は、浜松で自動車部品の製造工場をやっている。父孝一郎は、祖父惣介の始めた小さな自動車修理工場を引き継ぎ初めは地道に続けていたが、祖父の死後思い切って事業を拡大し、一代で今の会社を築き上げた。人間嫌いで人付き合いの苦手だった孝一郎が、良き仕事仲間に恵まれ、会社のために身を投げ出して働いてくれる社員を次々と採用し会社の業績を伸ばせた背景の原点には、彼自身の人生観を大きく覆す出来事があった。
それは出張先の宿舎で、孝一郎がロビーに電話をかけに降りてきたところやや騒々しく、仕方なく受付で場所を聞き外の公衆電話ボックスに出かけた時の事だった。当時はまだ携帯電話は普及しておらず、そのとき中で電話をしていたのはヘビメタパンク風ジーンズに身を包み、髪を赤く染め鼻ピアスのタトゥーをした若い男だった。鼻と耳が銀のチェーンでつながり、痛そうだった。
―――ついてないな。
その風貌に怖れをなし出直そうかと思ったが時間も遅く面倒なので、路上の石ころを蹴りながらボックスから離れてぶらぶらと数分待って、話し終えた男と入れ替わるようにボックスに入った。すると驚いたことに、帰りかけたその男が再びつかつかと戻ってきてボックスの扉を開け、中の孝一郎に話しかけてきたのだ。気分を害されたとすれば心外で、何を言われるのかと身構えた瞬間、彼の発した言葉に耳を疑った。
「お待たせしてすみませんでした。田舎のおばあちゃん、電話きってくれないもんで。」
そう言って青年が、深々と頭を下げて去って行ったのだ。一瞬孝一郎は固まってしまって、言葉を返すことが出来なかった。感動した。何と礼儀正しく誠実なのだろう。ああいった人種とは世界が違うと、むしろ先入観から彼らを避けていた自分の誤った価値観と浅はかさ、そして思い上がりが恥ずかしかった。
その時の貴重な体験を境に人を見る目が変わった孝一郎は、この世界は人と人とが助け合い共存していくものだと考えを改め、個人経営だった彼の工場には、気が付けば彼の人柄に惹かれた人材が集まり、県内指折りの成長企業として今や注目を集めている。まだ下請けだが親会社からの信頼も厚く、その会社株は東証一部上場の話もちらほら出始めている昨今だった。そんな父は常日頃から、将来的に一人息子の健太に後を継がせたいと考えていた。だから健太が、三年目になってもまだ一軍に上がれないことを、親として心配するどころか、『来年あたり、野球を辞めて浜松に帰ってきてくれるって、お父さんは楽しみにしているの・・・。』と、母にそっと聞かされた時、健太は少なからずショックを受けたのだった。
―――見ていてくれ親父、オレは必ず這い上がるから!。
と、並々ならぬ決意で臨んだ今シーズンだったが、今年も一軍の試合は、残すところ三十数試合になってしまった。
「石黒、ちょっと来い!」
グラウンドを3周ランニングし終えたところで、監督に呼ばれた。今日の練習の総括だ。
「お前は、本当に守備のセンスがいい。あの伝説の広岡さんにも、ヒケはとらんぞ。」
初めに思いっきり褒められた。あとが恐い。
「だがなぁ、守備だけじゃメシは食えんぞ。何だあのバッティングは。空振りをせんだけで、つまり全部当てるだけで前に飛ばんじゃないか。外角は流せ、真ん中はセンターに打ち返せ、内角は引っ張れ。お前には一言だけだ。初心に帰って、前に飛ばせー!以上。」
二軍監督の宮原は、かつてヨクルートスパローズでその華麗な守備で鳴らし、〝名ショート〟と謳われた男で、どちらかと云えば打つことより守りに重点を置いた指導方針だった。健太のことも、その守備力と走力をかって、7月にいちど一軍入りを推薦してくれたのだ。しかし、一軍監督の名将村野はそのバッティングを見て、ひと言「話にならん!」と、一笑に付した。三冠王を何度も取った村野から見れば、前に飛ばない健太のバッティングは基本や素質以前の問題だったのだろう。7月のその日以来、健太の一軍入りは、また遠のいたのである。



書籍のご感想や著者へのご質問など何でもご自由にご記載ください。
(コメントの投稿にはFacebookへのログインが必要となります。)