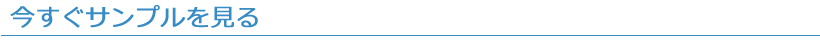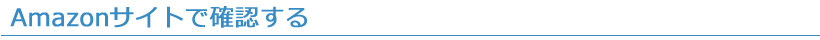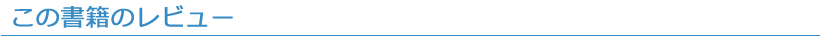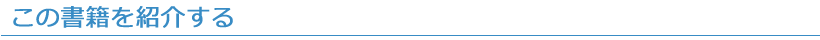AI音声解説
再生ボタンを押すとAI音声のナレーションを聞くことができます。
読売新聞に取材されました!


(記事一部抜粋)
土井さんは、「90歳を超えた男性高齢者が書いた本は少ないのではないか。この年でもその気になれば、電子書籍だって出せるよと伝えたい。」と話している。

奈良新聞に取材されました!


(記事一部抜粋)
90歳を超えたお年寄りの単なる回想録などではなく、「現代史に残る出来事や人物との遭遇の証人」としての記録性と、介護される生活における男性側の心理や葛藤を率直に綴(つづ)った記録性という「2つのリアル」を内包した読み物である。

サンデー毎日に取材されました!


(記事一部抜粋)
旧制中学時代の同級生2人が、90歳を超えてから戦争体験や老いの日常を綴った共著を3冊刊行した。直近に出版したのは電子書籍『同行二人-93歳のふたり言』。94歳になった2人は今年中にあと1冊を、と意気込んでいる。


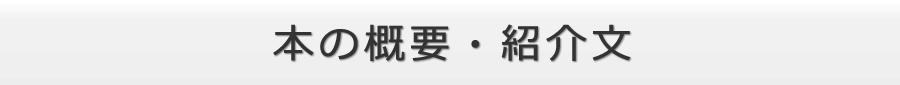

視力を失った菊池寛賞ジャーナリストと、旧制中学の同級生が協力して綴った24の物語。
三島由紀夫、ドナルド・キーンほかの故人や事件の思い出と、93歳の現実(想いと日常)が交錯する。
徳岡が電話で送る頭の中の原稿を、土井が聞き取って文章化し、挟み込むように93歳のリアルを綴る。
超高齢化社会を生きるヒントか反面教師か?



同行二人
ー九十三歳のふたり言
徳岡孝夫
土井荘平
菊池寛賞ジャーナリストと、旧制中学の同級生が綴る二十四の物語。
三島由紀夫、ドナルド・キーンほかの故人や事件の思い出と、九十三歳の現実が交錯する。
同行二人
徳岡孝夫
「力道山の試合決まる、四国初」、「琴平で火事、三軒焼ける」、「戦後初の混雑ダイヤ、四鉄局」などという、読者にもっとも密着した記事だが、朝読んでも夕方には忘れられてしまう雑報が、私の四国生活の頃には新聞の最終ページに載っていた。それとは別に、力道山とシャープ兄弟の県営球場での試合日程などは折り込みになっていた。
その種の記事を書いて一生を送るのかと、紫雲丸事件で他社に抜かれるという大失敗をしたあとの私はそんな思いでいたが、思いがけず、大阪本社地方版編集係へ転勤の辞令が来た。
四国では、殺人事件もあったし、一家心中もあった。連絡船が沈んだというニュースもあった。あまつさえ将来の伴侶を見つけるという思いがけない運命の糸を手繰り寄せた。
四国に別れを告げる前にもう一度四国を見ておこう、という気が起こって、四鉄局(四国鉄道局)の記者クラブへ相談に行った。
そこにいたのはベテラン同僚広岡澄夫さん(小峰元の名で江戸川乱歩賞を取った人)だった。
「明日、四鉄局へ来なさい」というので、お言葉にしたがって翌日午後に四鉄局へ行った。
彼は私を連れて広報課へ行き、「昨日話した、これが徳岡君」と短く紹介すると、広報課の人は、「ああ、そうですか」と簡単に答えて、引き出しから小さい定期券のようなものを手渡し、「しっかり書いてください」と言って私に渡した。
それは、四国鉄道局管内で、四国四県を二等車(今のグリーン車のようなもの)に乗って自由に旅行できる魔法のような無料パスだった。
それまで三等しか乗ったことのない平記者の私は最敬礼して魔法の絨毯をもらって支局に戻った。
大阪本社へ赴任するまでの日数はごく短い。時間の余裕はあまりない。私は無料パスを使って松山へ行き、それで四国に別れを告げることにした。
ふとお遍路(へんろ)さんの歩く道を歩いてみようと考え、松山の郊外へ出た。
お遍路には、順打ちと逆打ち、大きく分けて二つの歩き方がある。
讃岐から出て時計回りに高知中村を廻り四万十川の源流に沿って松山を目指す。
四国は小さい世界だが、松山から高知までは、順打ちしても札所と札所の間にかなりの距離があり、弱い足のお遍路さんは苦渋するコースである。
やっと松山の市街地に入った。というところあたりに五十一番札所の石手寺という札所があり、私の行ったときは人気(ひとけ)がなかった。ご遍路を泊める何十畳敷きの大広間があったが人影はなかった。
中へ入ってみると、調度はまったくない。ただ壁に、畳二枚分ぐらいの大きな墨で書いた掲示があり、いろは順に、到着する郵便物の受け皿がならんでいた。しばしの間俗世間と縁を断つお遍路の手元にも届けねばならない家族のニュースなどがあるのだろう。
外へ出ると、小川が流れている。一人の若い婦人がしゃがんで青菜を洗っていた。今から遠路はるばるやってきて夕方に着くお遍路のための食事の準備だろう。
外はまだうすら寒い。四国の春とはいえまだ寒い季節だった。
青菜も洗っても積むほどの分量ではない。つつましい食事のようだった。
なぜかそれがとても美しく四国らしく、私は、「四国よさらば」とひそかにつぶやいて、寺を後にした。
それから三十年ほど後に、私は東京の「サンデー毎日」編集部に転属になっていたが、「グラビア・ルポ」を書く仕事がまわってきて、巻頭巻末八ページのグラビア写真の下に説明をつけ季節の随筆を書くという贅沢な仕事で、第一回は、「雪見列車」という題で北東北の冬を書いた。
蒸気機関車が列車を牽いていた時代で、「北海道の米では寿司は握れん」と意気盛んなオバサン族が両肩に何斗かの米を背負い、青函連絡船の桟橋を雪に滑らないよう足を踏みしめながら船へ向かっていた時代である。
私は一週間東北を歩き、その見聞を記事にした。意外に評判のいい記事だった。
三十年前の四国松山への旅も、それと同じような短い紀行文を書くつもりで松山へ出掛けたのだった。
それが石手寺で思いもかけず青々とした菜に出会った。もう四国で記者をすることもあるまいとセンチメンタルな気になって青菜を眺めた。
お遍路といっても他人が思うほど容易いものではない。いつもお天気とは限らないし、親戚に頼んで路用金を送ってもらわねばならない羽目に陥ることもある。体の調子が悪くなるときもある。鷹揚な四国の住人も全員がお遍路に同情しているとはかぎらない。「お遍路法度」と書いた家もある。急病人がでたときなどの当然の断りだろうから責めることはできない。
そうかと思うと、「この先に風呂があります」と張り紙があったり、老婆らしき手で「おまめさんのたいたんのおふせがあります」と書いた半紙が張ってある家もある。
足が疲れるのは当然のことで、そういうときにも遍路の旅は「お大師さん」と二人連れという気持ちを乗せて、修行の旅をする。
お遍路は、出発を前に、「同行二人」(どうこうににん)という文字を脚絆や笠に書いておく。私は花見旅行をしているのではない。お大師さん、弘法大師さま、と二人連れ、という意味で「同行二人」と書いて、わずかな喜捨を求めるのである。
私は、東北のグラビア・レポの次に、懐かしい四国を同じような記事にしようと思いつき四国をたずねた。
しかし再訪した四国は、三十年という歳月を経て様子が一変していた。すっかり観光地と化した石手寺のそばには、青菜を洗っている姿はなく、小さな店が並んでいた。また大広間の郵便受けは、いろは順からアイウエオ順に変わっていた。私は倉皇として背を向けた。
今私は、「同行二人」でお遍路さんのように人生の終末期を歩いている思いである。私の同行者は、お大師さま、ではない。同じ今年九十三歳、旧制中学の同級生土井荘平君である。
数年来、二人で共著本を作ってきた。しかも失明に近い私が電話で口述する話を土井君が文章化するというやり方で本を作り、また雑誌などの原稿をも綴ってきた。そのために毎日何度も電話会話をする。それにつれて、本の原稿だけではなく、天下国家のことも話す。お互いの体のことも話す。阪神タイガースの現状も話す。さらには家族にも言えない心の中も話す。まさに、「同行二人」の旅路である。
私は本書では触れ合って知遇を得た人たちとのつきあいを中心にして思い出を語りたいと思う。土井君はこのトシの「現実と思い」を書くだろう。
老いての友と、慕わしきひとと
土井荘平
徳岡孝夫と私は、ともに妻に先立たれた。徳岡は一戸建てに住むが、母屋に息子を住まわせての離れ室に暮らし、私はマンションの独り暮らしをしている。
ある日のふたりの、故郷の大阪弁での会話。
「モシモシ、原稿のつづき、行くわ。スマンなあ」と徳岡。
「おい、そのスマンはナシや」と私。
「いや、ウラ取りなんかもあってキミの負担が重いのは分かってるから、つい」
「負担が重いとかそんなことナシや」
「そやけど、今回はただの口述筆記じゃない。知遇を得た人の思い出を書きたいのだが、三島由紀夫にしたって、キーンさんも、ストークスも、一度詳細に書いた本を出してる。まだ書いていないで、ボクのみが知る事実や思いなどを書くつもりやが、その背景も書く必要がある。ボクはもうまったく本を読めないから自分で旧著を点検でけヘン。今口述すると同じことを同じ文章か、似た文章で書いてしまう可能性が高い。そんな二重書きを防ぐために、キミに、ボクの旧著何冊かを丹念に再読してもらい、ダブっての記述は削除して再構成するとか、一部は明記したうえで引用するとか。書き直さないといけない。その相談に乗ってもらうという余分なことも頼まんならん」
「そんな気遣い、いらん。これ始めてなかったら、たぶんボクは一日中電話一本かからん暮らししてたやろう。こっちが感謝や」
「そう言うてくれると助かるわ。まあ慣用句や、思うてくれ」
「そんな慣用句、いらんわ」
徳岡の電話での口述を録音し文章化する毎日である。
令和二年に徳岡との共著で「夕陽が丘ー昭和の残光」(鳥影社刊)を上梓した。十五歳、旧制中学四年生にて太平洋戦争の終戦に遇った私たちの世代の「昭和」を綴ったもので、徳岡が過去雑誌に書いた膨大なエッセーから選んだものと私がシニア誌などに書いたものを並べ、書き下ろしも加えた。
視力を失いつつあった徳岡の書き下ろし文は、彼の口述を私が筆記して作り上げた。
翌年、徳岡から、「百歳以前」という一書を編もうとの提案があった。
「長寿になったといっても、定年から結構長い百歳以前をどう生きるかだよ」という徳岡が記憶に残る事件と提言を書きたいと言う。その徳岡の文に差し込むように、私は九十歳を超えたやもめ男の日常と想いを書くことにした。
前作と違って全編書き下ろしである。徳岡が電話で送稿し、私が書きまとめるという原稿作りを毎日やり続けた。その合間に私は自分のチャプターを書いた。
こうしてつくり上げた「百歳以前」は、令和三年秋、「文春新書」にて発行されたが、新聞各紙や週刊誌でも紹介、書評をいただいた。
毎日新聞の滝野隆浩氏がコラム「掃苔記」で「百歳以前をどう生きる」と題して「…仕事に明け暮れた過去を懐かしむ一方で、老いて支えられる実生活がある。これこそが昭和ヒトケタ生まれのオトコたちの、いまのリアルな実情なのだ」と解読されていた。
またRSKラジオ「今月のおススメの一冊」にて、取り上げていただいた河野通和氏(元中央公論編集長)は、ブログ「読書日記」でも、「『男おひとりさま』朋友とともに山を下る」と長文の紹介を書いてくださっていたのだが、それを読んで、ロシア文学の泰斗、亀山郁夫氏が、その著書「人生百年の教養」(講談社現代新書)の中で、たいへんな賛辞をくださった。
そんな反響に勇気を得て、私たちは次作の執筆を進めている。
しかも、今回は、このトシで、電子書籍、さらにPОD本の出版を、独力でやるつもりである。
絶筆になるかもしれず、早く書き上げたいとの思いは当然あるが、一方では、そのプロセス、本を作っていくプロセスをいつくしむ思いもある。この過程こそが九十歳超の生きがいなのだから。
私のそんな日常はかなり忙しい。老いた人間のあまたの悩みに沈む時間をかなり消してくれる。
「あっ、携帯に電話や。ほら、亡くなった同級生のHの妹や」と私。
「出んでええんか」と徳岡。
「どうせ長話になるさかい、あとでこっちから電話、入れるわ。出なかったらキミと仕事中や、分かってくれてるから大丈夫や」
「どっちにしても、キミ、女出入りが多いから、原稿、進まんがな」
「女出入り? 古いことばやなあ。もう死語ちゃうか」
「その、でいり、やなくて、出はいりのほうや。毎週来てくれる福祉関係の女性、好きなんやろ。ヘルパー派遣事務所にも好きな女がおるんやろ。それに、デイサービスで行く老健にも好きなひと、おるんやろ。気が多すぎるんチャうか」
「いやいや、ケアマネ、介護士、リハビリの療法士、栄養士、事務所のひと。それぞれに個性があって、男として生きる人生の残りの少なさが始終頭の中に存在する身には、どの個性もいとおしい。好きな女性だらけや。独り暮らしでひととの会話に飢えてるから、話しかけてくれる人がいたら、喜んで話す。だから週一のデイサービス、一日が終わると、グータッチでもしたくなる哀歓がある。スタッフにしてみれば毎日のことで仕事や。しかし芝居であっても、この次会えるのはいつ? と別れは惜しんでくれるんや。うれしいやないか。そこには、ひとり、大好きになったひと、好き、というより、慕わしいひとというか、そんなひとがいたハルんや。まあ、そのことは、またにするけど」
「聞いてもいいよ」
「いや、別の機会にするよ。長話になるサカイ、それこそ進行の妨げや」
「ほんなら、書けよ」
「そうやなあ。その大好きになったひとへの思いやけど、トシをとると童心にかえるっていうけど、小学生のオレと担任の先生、というのに似てるなあ。その女先生が好きで好きでヒイキして欲しいんだが、先生はみんなの先生や。たまには頭を撫でてくれるときもあって血が上ったりするんやけど、ほかの同級生の男の子と話しているのが見えるとメラメラ嫉妬もする。一日中いっぺんも声さえかけてもらえないときもある。それも、帰るときに、今日は一度もお話、しなかったわねぇ。とでも聞いたら、別れの哀歓とともに次への期待が膨らむんだよ。ひょっとすると女房の化身を見ようとしてるのかなあ。彼女の後ろ姿にハッとするときなどあるんだよなあ」
徳岡「そんな理屈、つけてるのか」………
仕事も違ったし、時々会ったり電話で話したりすることはあったが、ずうっと親密なつきあいを続けてきたわけではなかった。
それがここ何年か前からは、来る日も来る日も、一日何度も電話で話している。こうなると会話は原稿だけではなくなった。
こういう日々が、一日でもながく続くことを願う、今日この頃である。

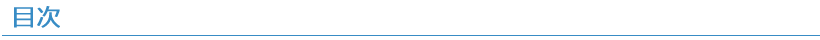

-
同行二人
- 徳岡孝夫
-
老いての友と、慕わしきひとと
- 土井荘平
-
ドッペルゲンガー
- 土井荘平
-
ドナルド・キーン
- 徳岡孝夫
-
ポール・ブルーム
- 徳岡孝夫
-
グータッチ
- 土井荘平
-
大阪船場・島之内
- 徳岡孝夫
-
大阪ミナミ
- 土井荘平
-
ヘンリー=スコット・ストークス
- 徳岡孝夫
-
SNS
- 土井荘平
-
立花 隆「徹底的な質問者」
- 徳岡孝夫
-
切れた絆をつなぐ
- 土井荘平
-
アイアコッカ
- 徳岡孝夫
-
一難去らず、また一難
- 土井荘平
-
「老衰」の前に
- 土井荘平
-
終戦のあとさき
- 徳岡孝夫
-
ベトナム戦争時の「B二九」
- 徳岡孝夫
-
おしろいが密かに深紅
- 土井荘平
-
夜の思想
- 徳岡孝夫・土井荘平
-
夢芝居
- 土井荘平
-
山崎豊子「お豊さん」
- 徳岡孝夫
-
終幻夢(ファンタジー)
- 土井荘平
-
三島由紀夫「心々ですさかい」
- 徳岡孝夫
-
付記 加登屋のひとり言ー徳岡孝夫さん
- 加登屋陽一
- 初出雑誌
- 引用書籍および参照書籍
- 著者情報

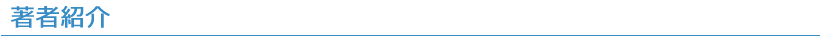

昭和四年十二月生。商社勤務、自営をへて、リタイア後、小説、エッセーなどの著述。
著書 「青い春、そして今晩秋」(「鶴」シニア文学大賞受賞)、「関西弁アレコレばなし」、「#戦争、平和、オートフィクションー昭和者がたり」ほか。
徳岡孝夫との共著に、「百歳以前」(文春新書)、「夕陽ケ丘ー昭和の残光」。
両人は、大阪府立北野(旧制)中学の同級生。

昭和五年一月大阪生。菊池寛賞受賞ジャーナリスト。
毎日新聞社で社会部、「サンデー毎日」、「英文毎日」記者、編集次長、編集委員などを歴任。「ニューヨーク・タイムズ」のコラムニストも務めた。
著書 「五衰の人ー三島由紀夫私記」(新潮学芸賞受賞)、「横浜・山手の出来事」(日本推理作家協会賞受賞)ほか多数。訳書 トフラー「第三の波」ほか多数。


書籍のご感想や著者へのご質問など何でもご自由にご記載ください。
(コメントの投稿にはFacebookへのログインが必要となります。)